ヘルメットの種類を紹介!バイク・工事・防災用など
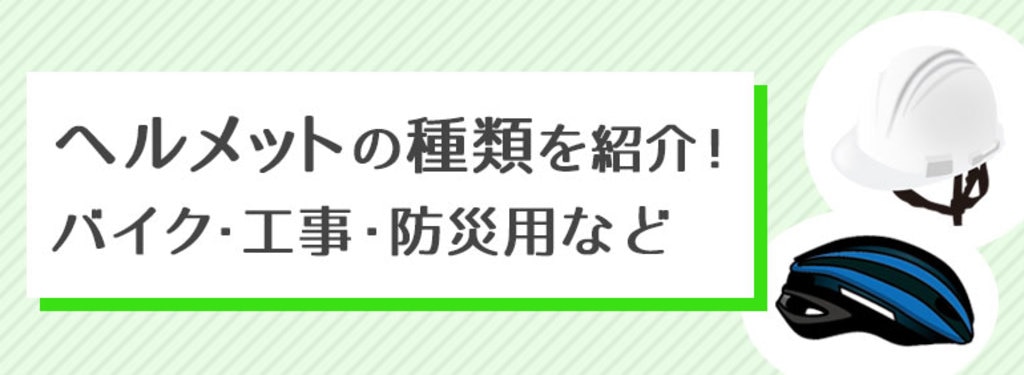
人体の中で最も重要な器官の一つといえば脳です。そして、その人体の中枢であるその脳があるのはもちろん頭部ですが、頭部は人体の最も高い位置にあり、また重い上に細い首だけで支えられています。そのため、ちょっと転んだだけでもダメージを受けやすい、いわば急所です。
もし頭部にわずかでもダメージを受ければ、それは即生命の危機に繋がってしまう危険性があります。そのためスポーツや工事、各種作業など、何かしらの頭部にダメージを受ける可能性がある場合には、あらかじめリスクに備え頭部を何らかの方法で保護しておく必要があるのです。
そして、その頭部を衝撃などから保護してくれる防護具といえばもちろんヘルメットです。ヘルメットにはオートバイ用、自転車用、その他スポーツやアクティビティの際に使用されるもの、さらに工事や作業の際に必要なものまで様々なものがあります。同じ頭部を保護するものですが、用途が細かく分かれているというのはそれぞれに目的と、機能に違いがあるからにほかなりません。しかし種類が多い分何をどう選んでいいのか分かりにくいともいえるでしょう。
そこで、ここではヘルメットの種類の違いと、その選び方のポイントに焦点をあてて紹介していきましょう。
もし頭部にわずかでもダメージを受ければ、それは即生命の危機に繋がってしまう危険性があります。そのためスポーツや工事、各種作業など、何かしらの頭部にダメージを受ける可能性がある場合には、あらかじめリスクに備え頭部を何らかの方法で保護しておく必要があるのです。
そして、その頭部を衝撃などから保護してくれる防護具といえばもちろんヘルメットです。ヘルメットにはオートバイ用、自転車用、その他スポーツやアクティビティの際に使用されるもの、さらに工事や作業の際に必要なものまで様々なものがあります。同じ頭部を保護するものですが、用途が細かく分かれているというのはそれぞれに目的と、機能に違いがあるからにほかなりません。しかし種類が多い分何をどう選んでいいのか分かりにくいともいえるでしょう。
そこで、ここではヘルメットの種類の違いと、その選び方のポイントに焦点をあてて紹介していきましょう。
目次
1章:ヘルメットの基本構造
2章:バイク用ヘルメットの種類・選び方のポイント
3章:工事用ヘルメットの種類と特徴
4章:防災用ヘルメットの種類・選び方ポイント
5章:その他・スポーツ用ヘルメットの選び方
まとめ
1章:ヘルメットの基本構造
破壊されることで衝撃を吸収する
とてもシンプルな構造をしており、バイク用や作業用など細かな違いはありますが基本どれも似ています。まず、丈夫な外殻があり、その中は衝撃を吸収する構造となっています。そして頭に固定するためのハンモックやストラップ(アゴひも)などが基本構成となっています。
そのなかでも外殻部分、いわばヘルメット本体ともいえるのが帽体(シェル)です。素材はABSやポリカーボネート、ポリチレンやFRPなどの樹脂でできており、軽量で衝撃に強い構造を持っています。
そしてヘルメットの内側は、発泡スチロールなどでできた衝撃吸収ライナーになっています。万が一ヘルメットに衝撃を受けた場合には、この帽体本体と衝撃吸収ライナーが破壊されることで衝撃を吸収し、頭部を保護するという構造になっています。
そのなかでも外殻部分、いわばヘルメット本体ともいえるのが帽体(シェル)です。素材はABSやポリカーボネート、ポリチレンやFRPなどの樹脂でできており、軽量で衝撃に強い構造を持っています。
そしてヘルメットの内側は、発泡スチロールなどでできた衝撃吸収ライナーになっています。万が一ヘルメットに衝撃を受けた場合には、この帽体本体と衝撃吸収ライナーが破壊されることで衝撃を吸収し、頭部を保護するという構造になっています。
2章:バイク用ヘルメットの種類・選び方のポイント
安全基準をクリアしているか確認を
ヘルメットが必ず必要なシチュエーションと言われて、誰もが最初にイメージするのはオートバイに乗る際ではないでしょうか。当然のことですが、オートバイに乗る場合にはヘルメットの装着は義務です。でもヘルメットであればどんなものでもいいというわけではなく、安全基準をクリアしたものでないと危険です。道路交通法では以下の7つの項目で基準が定められています。
●オートバイ用ヘルメットの安全基準
①左右、上下の視野が十分とれること。
②風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
③著しく聴力を損ねない構造であること。
④衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
⑤衝撃により容易に脱げないように固定できるアゴひもを有すること。
⑥重量が2kg以下であること。
⑦人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
これらの条件を満たしたヘルメットには、「PSCマーク」と「SGマーク」が付いています。
②風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
③著しく聴力を損ねない構造であること。
④衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
⑤衝撃により容易に脱げないように固定できるアゴひもを有すること。
⑥重量が2kg以下であること。
⑦人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
これらの条件を満たしたヘルメットには、「PSCマーク」と「SGマーク」が付いています。

ちなみにPSCマークは、これがないとそのヘルメットを販売してはいけない事になっています。オートバイ用ヘルメットでこのマークがないものは装飾用であり頭を保護する機能は期待できないと考えていいでしょう。
もう一方のSGマークは、製品安全協会の安全基準を満した製品に付けられる安全性を保障するものです。このマークがあるヘルメットを使用していて、もし商品の欠陥などが原因による人身被害があった場合は賠償措置が実施されます。ただしSG規格が定めたヘルメットの性能を超える強い衝撃(レースによる事故など)を受けた場合などは補償の対象外となります。
PSCマークはないとオートバイ用ヘルメットとして販売ができませんが、SGマークは任意のもの。なくてもオートバイ用ヘルメットとして販売できます。しかし、日本で流通しているヘルメットでPSCマークがあってSGマークのないものはほとんどありません。ですからこれらマークはセットで表示されているものと思っていいでしょう。
輸入ヘルメットの中にはこのPSCやSGマークが取得されていないものもあります。海外の規格をクリアしていれば安全性に問題がないかもしれません。またマークがなくても厳密には道路交通法では取り締まられることもありませんが、万が一のリスクを考え国内での着用は避けたほうがいいでしょう。
もう一方のSGマークは、製品安全協会の安全基準を満した製品に付けられる安全性を保障するものです。このマークがあるヘルメットを使用していて、もし商品の欠陥などが原因による人身被害があった場合は賠償措置が実施されます。ただしSG規格が定めたヘルメットの性能を超える強い衝撃(レースによる事故など)を受けた場合などは補償の対象外となります。
PSCマークはないとオートバイ用ヘルメットとして販売ができませんが、SGマークは任意のもの。なくてもオートバイ用ヘルメットとして販売できます。しかし、日本で流通しているヘルメットでPSCマークがあってSGマークのないものはほとんどありません。ですからこれらマークはセットで表示されているものと思っていいでしょう。
輸入ヘルメットの中にはこのPSCやSGマークが取得されていないものもあります。海外の規格をクリアしていれば安全性に問題がないかもしれません。またマークがなくても厳密には道路交通法では取り締まられることもありませんが、万が一のリスクを考え国内での着用は避けたほうがいいでしょう。
●オートバイ用ヘルメットの種類と特長
オートバイ用のヘルメットといってもその種類や規格、メーカーは多種多様です。どれを選べばいいのか判断は容易ではありません。形状に関しては大きく以下のようなタイプに分かれます。
・ハーフタイプ
・ジェットタイプ
・フルフェイスタイプ
・システムタイプ
安全基準をクリアしていることは当然ですが、これらのタイプの中から、自分のオートバイの排気量やスタイルに合ったものを選ぶといいでしょう。ではどのようなオートバイに、どんなタイプのヘルメットが適しているのか、それぞれの特長について紹介します。
・ハーフタイプ
・ジェットタイプ
・フルフェイスタイプ
・システムタイプ
安全基準をクリアしていることは当然ですが、これらのタイプの中から、自分のオートバイの排気量やスタイルに合ったものを選ぶといいでしょう。ではどのようなオートバイに、どんなタイプのヘルメットが適しているのか、それぞれの特長について紹介します。
●ハーフタイプ
半キャップ型、お椀型とも呼ばれるのがハーフタイプのヘルメットです。かぶるのが簡単で、開放感もあり比較的安価なものが多いのが特長です。ただし帽体は頭の上半分を覆うだけなので、顔や後頭部などは保護してくれません。
安全規格をクリアしたものでも、125cc以下用として販売されているのがほとんどで、原付スクーターなどのライダーによく使用されています。解放感は高く視界は優れていますが安全性という意味ではあまり期待できません。高速道路の走行が可能な126cc以上のバイクでは使用するべきではないでしょう。
安全規格をクリアしたものでも、125cc以下用として販売されているのがほとんどで、原付スクーターなどのライダーによく使用されています。解放感は高く視界は優れていますが安全性という意味ではあまり期待できません。高速道路の走行が可能な126cc以上のバイクでは使用するべきではないでしょう。



●ジェットタイプ
オープンフェイスヘルメットともいわれるのがジェットタイプです。帽体は頭から後頭部までをカバーしてくれるので安全性も比較的高いと言えるでしょう。顔の部分はオープンフェイスの名の通り、空いているので視界が良いという特長もあります。
顔部分を覆う透明のシールドがついたものと、ないものがあります。シールドがあるものは空力にも優れており、高速道路走行でも快適です。帽体が、アゴ部分をカバーしないため、安全性ではフルフェイスに一歩劣るとされていますが、かぶりやすく脱ぎやすいというメリットがあります。
比較的どのようなオートバイにも似合い、大排気量のスポーツバイクから、オフロードバイクや大型スクーター、ハーレーなどのアメリカンバイクなどのライダーにも愛用されている方は少なくありません。
顔部分を覆う透明のシールドがついたものと、ないものがあります。シールドがあるものは空力にも優れており、高速道路走行でも快適です。帽体が、アゴ部分をカバーしないため、安全性ではフルフェイスに一歩劣るとされていますが、かぶりやすく脱ぎやすいというメリットがあります。
比較的どのようなオートバイにも似合い、大排気量のスポーツバイクから、オフロードバイクや大型スクーター、ハーレーなどのアメリカンバイクなどのライダーにも愛用されている方は少なくありません。

●フルフェイスタイプ
最も安全性が高いと言われているのがフルフェイスタイプです。帽体がアゴ部分を含め頭部全体を覆うってくれるのでどの方向からも頭部を守ることが可能です。そのため安全性が重視されるレースなどにも使用されています。
欠点としては頭から顔全体を覆うためジェットタイプのような開放感が得られないということ。そして着脱が他のタイプよりも少し面倒であるということでしょうか。また、重量に関してもが比較的重めです。
さらに覆う面積が多いため通気性が悪く、夏場などはヘルメットの中が蒸れてしまいがちです。
しかし最も重要な安全性という意味では非常に優れているので、大型バイクやスポーツバイクのライダーの方に多く使用されています。もちろん原付スクーターやオフロードバイクなどで使用しても問題はありませんが、頻繁に着脱をする近所の買い物などの用途に使用するには少し面倒かもしれません。
欠点としては頭から顔全体を覆うためジェットタイプのような開放感が得られないということ。そして着脱が他のタイプよりも少し面倒であるということでしょうか。また、重量に関してもが比較的重めです。
さらに覆う面積が多いため通気性が悪く、夏場などはヘルメットの中が蒸れてしまいがちです。
しかし最も重要な安全性という意味では非常に優れているので、大型バイクやスポーツバイクのライダーの方に多く使用されています。もちろん原付スクーターやオフロードバイクなどで使用しても問題はありませんが、頻繁に着脱をする近所の買い物などの用途に使用するには少し面倒かもしれません。
●システムタイプ
最近人気となっているのがシステムタイプです。これは基本がフルフェイスタイプで、その前面部が大きく開閉できるデザインになったヘルメットです。つまり、装着時はフルフェイスタイプの安全性や防風性が期待でき、着脱時や駐車中はオープンフェイスタイプの解放感得られるという良いとこ取りのヘルメットということです。
ただし、開閉機構を持つという構造上、全体が大きくなりがちで、また安全性に関してもフルフェイスと同等というわけではありませんのでその点は注意が必要です。
ただし、開閉機構を持つという構造上、全体が大きくなりがちで、また安全性に関してもフルフェイスと同等というわけではありませんのでその点は注意が必要です。
●オートバイ用ヘルメットの選び方のポイント
オートバイ用ヘルメットにはSGやPSC以外にもより厳しい様々な安全基準があります。それがJISやSNELL、ECEなどです。またAraiなどメーカー独自の安全基準を設けているものもあります。
これらはPSCやSGよりもさらに厳しい規格で、PSCとSGはいわばオートバイ用ヘルメットとして最低限の安全規格、PSCとSGマークがある上にこれらのより高い基準をクリアしたヘルメットのほうが間違いなく安全です。しかし、その分重かったり、高価なものの多いので、どのようなバイクでもこの厳しい規格をクリアしたヘルメットを使用するべき、ということはありません。
基本は基本となる安全基準をクリアしたヘルメットの中から、オートバイの使い方や、使用しているオートバイのタイプに合わせて選ぶのがオススメです。
例えば原付バイクであれば、高額なフルフェイスヘルメットは大げさかもしれません。手軽で安全性も高いジェットタイプがおススメです。もっと手軽なものが良いという場合は、軽量で着脱も楽、解放感も高いハーフタイプを選ぶという選択肢もあります。しかしハーフタイプは安全性という意味では余り期待できない、ということをキチンと理解したうえで使う必要があるでしょう。
大排気量車やロングツーリング目的にはフルフェイスタイプがおススメです。できればJISやSNELLなど高い基準の安全性が確保されたものがベストでしょう。また通気性に優れたベンチレーション機能や、高速走行時に風切り音などを抑えてくれる空力デザインなどにも注目しましょう。フルフェイスは帽体の面積が大きく、カラーやデザインも豊富なのでオートバイのデザインにマッチしたものを選ぶ楽しみもあります。
ビッグスクーターや街乗りのオートバイであれば解放感があって、安全性も高いシールドのあるジェットタイプやシステムタイプが適しているでしょう。アメリカンバイクならシールドのないジェットタイプが似合うかもしれせん。ゴーグルなどを合わせてアクセサリー的なコーディネートを楽しむのも良いかもしれません。
これらヘルメット購入の際に大事なポイントがサイズです。オートバイ用ヘルメットは、頭の外周サイズ(まゆの上、おでこのいちばん高い位置から水平に後ろに回した位置まで。)を基準にM(57-58cm)などのサイズで分けられていますが、同じMサイズでもメーカーによって微妙な違いがあります。
かぶった時にきつすぎるのもつらいですが、頭を振って容易にズレるようではいけません。万が一強い衝撃を受けた際外れてしまったらアゴひもに強い力がかかってのどにダメージを与えてしまうこともがあります。自分の正しいサイズを知り必ず試着を行うようにしましょう。
これらはPSCやSGよりもさらに厳しい規格で、PSCとSGはいわばオートバイ用ヘルメットとして最低限の安全規格、PSCとSGマークがある上にこれらのより高い基準をクリアしたヘルメットのほうが間違いなく安全です。しかし、その分重かったり、高価なものの多いので、どのようなバイクでもこの厳しい規格をクリアしたヘルメットを使用するべき、ということはありません。
基本は基本となる安全基準をクリアしたヘルメットの中から、オートバイの使い方や、使用しているオートバイのタイプに合わせて選ぶのがオススメです。
例えば原付バイクであれば、高額なフルフェイスヘルメットは大げさかもしれません。手軽で安全性も高いジェットタイプがおススメです。もっと手軽なものが良いという場合は、軽量で着脱も楽、解放感も高いハーフタイプを選ぶという選択肢もあります。しかしハーフタイプは安全性という意味では余り期待できない、ということをキチンと理解したうえで使う必要があるでしょう。
大排気量車やロングツーリング目的にはフルフェイスタイプがおススメです。できればJISやSNELLなど高い基準の安全性が確保されたものがベストでしょう。また通気性に優れたベンチレーション機能や、高速走行時に風切り音などを抑えてくれる空力デザインなどにも注目しましょう。フルフェイスは帽体の面積が大きく、カラーやデザインも豊富なのでオートバイのデザインにマッチしたものを選ぶ楽しみもあります。
ビッグスクーターや街乗りのオートバイであれば解放感があって、安全性も高いシールドのあるジェットタイプやシステムタイプが適しているでしょう。アメリカンバイクならシールドのないジェットタイプが似合うかもしれせん。ゴーグルなどを合わせてアクセサリー的なコーディネートを楽しむのも良いかもしれません。
これらヘルメット購入の際に大事なポイントがサイズです。オートバイ用ヘルメットは、頭の外周サイズ(まゆの上、おでこのいちばん高い位置から水平に後ろに回した位置まで。)を基準にM(57-58cm)などのサイズで分けられていますが、同じMサイズでもメーカーによって微妙な違いがあります。
かぶった時にきつすぎるのもつらいですが、頭を振って容易にズレるようではいけません。万が一強い衝撃を受けた際外れてしまったらアゴひもに強い力がかかってのどにダメージを与えてしまうこともがあります。自分の正しいサイズを知り必ず試着を行うようにしましょう。
3章:工事用ヘルメットの種類と特徴
使用区分が合っているものを選びましょう
オートバイ用のヘルメットは転倒や衝突時に頭部を保護するためのもの。一方、工事などの現場や作業などの際に必要とされるヘルメットは、飛来物や落下物や、障害物への頭部への衝突、さらに転倒時の頭部への衝撃などを吸収して頭部への損傷を防ぐために使用されます。また電気作業の際にも、感電の危険を防ぐ目的にも使用されています。一般には安全帽や保護帽などと呼ばれています。
この保護帽は厚生労働省の「保護帽の規格」に適合し、なおかつ型式検定に合格しているものでなければ使用することができないとされています。合格しているものには検定合格標章「労・検」のラベルが貼付されており、さらにこのラベルには使用区分や材質などの項目も明記されています。
保護帽の種類は、厚生労働省の型式検定によってその使用区分決められており「飛来・落下物用」と、「墜落時保護用」の2種類があります。
飛来・落下物用の保護帽は、土木や建築の現場などで使用するもので、頭上から落ちてきた時に頭部を保護する目的の保護帽です。
墜落時保護用の保護帽は工事や作業の現場で墜落や転倒時頭部を保護するのが目的です。さらに、それぞれの保護帽には、電気作業や電線がある現場での作業時に、7000V以下の感電の危険から頭部を保護する「電気用」を兼用するものもあります。
オートバイ用ヘルメットと作業用の保護帽の大きな違いは着装体です。着装体とは保護帽の帽体を頭部に保持するためのヘッドバンドやハンモックなどの部品のこと。作業用保護帽はオートバイ用のヘルメットとは違い、帽体と着装体のハンモックの間に隙間があります。
保護帽が衝撃を受けた際には、外殻である帽体と発泡スチロールなどの衝撃吸収体の変形に加えて、この着装体のハンモックがこの隙間の間で伸びることで、衝撃を吸収する構造になっているのです。そのためしっかりとヘッドバンドの調節を行い、使用中ぐらついたりしないように装着しなくてはなりません。そうでないと保護性能を十分に発揮することができないので注意が必要です。
この保護帽は厚生労働省の「保護帽の規格」に適合し、なおかつ型式検定に合格しているものでなければ使用することができないとされています。合格しているものには検定合格標章「労・検」のラベルが貼付されており、さらにこのラベルには使用区分や材質などの項目も明記されています。
保護帽の種類は、厚生労働省の型式検定によってその使用区分決められており「飛来・落下物用」と、「墜落時保護用」の2種類があります。
飛来・落下物用の保護帽は、土木や建築の現場などで使用するもので、頭上から落ちてきた時に頭部を保護する目的の保護帽です。
墜落時保護用の保護帽は工事や作業の現場で墜落や転倒時頭部を保護するのが目的です。さらに、それぞれの保護帽には、電気作業や電線がある現場での作業時に、7000V以下の感電の危険から頭部を保護する「電気用」を兼用するものもあります。
オートバイ用ヘルメットと作業用の保護帽の大きな違いは着装体です。着装体とは保護帽の帽体を頭部に保持するためのヘッドバンドやハンモックなどの部品のこと。作業用保護帽はオートバイ用のヘルメットとは違い、帽体と着装体のハンモックの間に隙間があります。
保護帽が衝撃を受けた際には、外殻である帽体と発泡スチロールなどの衝撃吸収体の変形に加えて、この着装体のハンモックがこの隙間の間で伸びることで、衝撃を吸収する構造になっているのです。そのためしっかりとヘッドバンドの調節を行い、使用中ぐらついたりしないように装着しなくてはなりません。そうでないと保護性能を十分に発揮することができないので注意が必要です。
●保護帽の材質の違い
保護帽の帽体は主に樹脂でできていますが、その樹脂の素材によって、特性が異なります。主な素材としては。ABS
(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーカーボネート)、FRP(グラスファイバー)、PE(ポリエチレン)などがあります。
屋外作業には建設現場などの屋外作業には全てのタイプが適していますが、高温作業には耐熱性に優れたFRPやPCが適しています。また低温作業には耐候性に優れたFRPが、そして油や薬品などを扱う現場にはFRPやPEが適しているとされています。
比較的汎用性の高いFRP製ですが、耐電性は高くないので、電気作業の際にはABS、PC、PE製で、なおかつ「電気用」兼用タイプを使用するようにしてください。また素材によってその耐用年数が変わってくることにも注意が必要です。ABS、PC、PEの場合は3年。FRPは5年が耐用年数とされています。また着装体は1年ごとの交換が推奨されています。樹脂は紫外線などで劣化が進むので見た目に変化が感じられなくてもある程度の期間使用したら交換するようにするべきでしょう。
(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーカーボネート)、FRP(グラスファイバー)、PE(ポリエチレン)などがあります。
屋外作業には建設現場などの屋外作業には全てのタイプが適していますが、高温作業には耐熱性に優れたFRPやPCが適しています。また低温作業には耐候性に優れたFRPが、そして油や薬品などを扱う現場にはFRPやPEが適しているとされています。
比較的汎用性の高いFRP製ですが、耐電性は高くないので、電気作業の際にはABS、PC、PE製で、なおかつ「電気用」兼用タイプを使用するようにしてください。また素材によってその耐用年数が変わってくることにも注意が必要です。ABS、PC、PEの場合は3年。FRPは5年が耐用年数とされています。また着装体は1年ごとの交換が推奨されています。樹脂は紫外線などで劣化が進むので見た目に変化が感じられなくてもある程度の期間使用したら交換するようにするべきでしょう。
●保護帽のかぶり方
保護帽の正しいかぶり方は、まず保護帽をまっすぐ、かつ深くかぶります。その際、あまり後ろや前に傾けてかぶらないようにします。次に後ろ側にあるヘッドバンドの調節機能を使った頭の大きさにフィットさせます。緩みがないようにしっかりと固定してください。
最後にアゴひもを調節します。緩みがないようにしっかりと締めあす。保護帽の着用中は、アゴひもはゆるめたり外すのは厳禁です。万が一の際、保護帽が脱げてしまう危険性があります。
最後にアゴひもを調節します。緩みがないようにしっかりと締めあす。保護帽の着用中は、アゴひもはゆるめたり外すのは厳禁です。万が一の際、保護帽が脱げてしまう危険性があります。
●デザインにもバリエーションのある保護帽
保護帽は材質による違いだけでなく形状にも様々なバリエーションがあります。工事現場のヘルメット(保護帽)というと、昔ながらの黄色いお椀型のもののイメージが強いですが、最近はツバ付きのオシャレなもの、バイザー付きのものなどもあり、それぞれには材質のバリエーションも用意されています。選ぶ際はまず用途にマッチしたタイプを選び、その上でデザインや材質などで自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。
形状のタイプの主なものは以下になります。
形状のタイプの主なものは以下になります。

●ツバなしタイプ
昔ながらのスタンダードなタイプ。ツバがないので視界を妨げず、かつ障害物へひっかかる危険も小さく、コンパクトなのが特長です。

●ツバつきタイプ
ツバによって日よけ効果が期待でき、また上方からの落下物にもツバが顔面をある程度保護してくれます。

●クリアバイザー付きタイプ
ツバつきタイプの、ツバの部分を透明にすることで上方の視界確保したタイプです。

●シールド付きタイプ
目を保護してくれるスライダー式のシールドを内蔵したタイプです。飛来物や薬品などから、顔を保護してくれます。
このように保護帽にはその使用区分のほか、材質やデザインに違いがあるので、その特長を理解して、作業内容に適したものを選ぶようにしましょう。また購入の際はオートバイ用のヘルメットと同様に一度試着してみることをオススメします。
4章:防災用ヘルメットの種類・選び方ポイント
ヘルメットにも消費期限がある?
自然災害の多い日本では、防災用のヘルメットも重要です。専用の物もありますが、多くの場合は工事や作業に使用される保護帽が防災用に使用されることが多いようです。こういったものは、使う機会はあまりありませんが、いざという時にあると心強いアイテムといえるでしょう。特に地震の際にはビルなどの建物からの落下物の危険があるので、頭部の保護は欠かせません。
地震が発生したあとに外を歩く際には、頭部を守る必要がありますが、手元に何もない場合はカバンやクッションなどを使うしかありません。しかし防災用のヘルメットを準備しておけば避難場所への移動の際にも両手が使え、安全性も高まります。
地震が発生したあとに外を歩く際には、頭部を守る必要がありますが、手元に何もない場合はカバンやクッションなどを使うしかありません。しかし防災用のヘルメットを準備しておけば避難場所への移動の際にも両手が使え、安全性も高まります。
●気をつけるべきは安全性と耐用年数
最も重要なことは安全性です。落下物から頭部を確実に守れるかどうかで選びましょう、そこでチェックするのが保護帽選びのパートで説明した国家検定合格品である証明の「労・検」のマークです。この飛来・落下物用の検定に合格したものなら防災用にも適しています。
デザインや素材などに関しては好みで選んでかまわないでしょう。普段使わないものなので耐用年数にも気をつけましょう。素材がABS、PC、PEの場合は3年。FRPは5年が耐用年数とされています。また着装体は1年ごとの交換が推奨です。使用する頻度が高くないので、厳密にこの通りである必要はありませんがあまり古い物だと本来の機能を果たせない可能性があります。
もちろん何もないよりもましですが、ある程度の期間を過ぎたヘルメットは交換を考えたほうがいいかしれません。
デザインや素材などに関しては好みで選んでかまわないでしょう。普段使わないものなので耐用年数にも気をつけましょう。素材がABS、PC、PEの場合は3年。FRPは5年が耐用年数とされています。また着装体は1年ごとの交換が推奨です。使用する頻度が高くないので、厳密にこの通りである必要はありませんがあまり古い物だと本来の機能を果たせない可能性があります。
もちろん何もないよりもましですが、ある程度の期間を過ぎたヘルメットは交換を考えたほうがいいかしれません。

●折りたたみヘルメットもおすすめ
防災用の専用ヘルメットには、専用の物として折りたたみタイプの物もあります。こういったタイプであれば普段コンパクトに収納することができるので防災用品などとバッグなどの中に一緒にしまっておけるのでじゃまになりません。購入の際は必ず国家検定合格品を選ぶようにしてください。
5章:その他・スポーツ用ヘルメットの選び方
自転車でもヘルメットの着用習慣を

自転車に乗る際や、アウトドアスポーツに取り組む時にも頭部を守るヘルメットは必要です。特に自転車は身近なものでありながら、衝突や転倒すれば重大な事故になりかねない乗り物。
最近は死亡事故なども急増しており、その危険性は以前よりも注目されています。そのため、ヘルメットの需要も急増しているようです。オートバイのように装着の義務はありませんが、万が一のことを考えて自転車に乗る際はヘルメットをかぶる習慣をつけておくべきでしょう。
自転車用のヘルメットは大きく大人用と子ども用に分かれます。また大人用のヘルメットはロードバイク用やMTB用など用途に合わせた様々タイプがあります。
スポーツが目的であれば専用の物を選ぶのが良いでしょう。普段の通勤用としてはカジュアルなタイプのヘルメットがおススメです。一見、帽子に見えるようなデザイン性の高い物なら街中でも違和感がありません。
ヘルメットの選び方は、まずかぶってみて、前後左右にすき問がないかを確認してください。輸入品などの場合日本人の頭の形にフィットしないものもあるので試着してみるのが良いでしょう。またストラップをキチンと締めて違和感がないかもチェックしましょう。
最近は死亡事故なども急増しており、その危険性は以前よりも注目されています。そのため、ヘルメットの需要も急増しているようです。オートバイのように装着の義務はありませんが、万が一のことを考えて自転車に乗る際はヘルメットをかぶる習慣をつけておくべきでしょう。
自転車用のヘルメットは大きく大人用と子ども用に分かれます。また大人用のヘルメットはロードバイク用やMTB用など用途に合わせた様々タイプがあります。
スポーツが目的であれば専用の物を選ぶのが良いでしょう。普段の通勤用としてはカジュアルなタイプのヘルメットがおススメです。一見、帽子に見えるようなデザイン性の高い物なら街中でも違和感がありません。
ヘルメットの選び方は、まずかぶってみて、前後左右にすき問がないかを確認してください。輸入品などの場合日本人の頭の形にフィットしないものもあるので試着してみるのが良いでしょう。またストラップをキチンと締めて違和感がないかもチェックしましょう。

子供用の自転車ヘルメットの場合は、選ぶ上で大切なのは同じくサイズです。子供の頭は小さいのでジュニア用、幼児用など必ずサイズのマッチしたものを選んでださい。
かぶった際にずれたり、頭部に負担がかかったりするものは危険です。やはり店頭で試着するのがいいでしょう。また子どもは成長が速いので、それに合わせて適したものに買い替えるようにしましょう。帽体にはハードシェルタイプとソフトシェルタイプの二種類ありますが、安全性に関してどちらも問題ないとされています。子供が喜ぶデザインで選んでかまいません。
注意しなくてはいけないのが兄弟がいる場合です。ヘルメットも洋服のようについついお下がり使ってしまいがちですが、ヘルメットには耐用年数があります。使用から3年を超えたものはメーカーが交換を推奨しています。安易にお下がりを使うのは避けるべきでしょう。新しい物を用意してあげてください。
かぶった際にずれたり、頭部に負担がかかったりするものは危険です。やはり店頭で試着するのがいいでしょう。また子どもは成長が速いので、それに合わせて適したものに買い替えるようにしましょう。帽体にはハードシェルタイプとソフトシェルタイプの二種類ありますが、安全性に関してどちらも問題ないとされています。子供が喜ぶデザインで選んでかまいません。
注意しなくてはいけないのが兄弟がいる場合です。ヘルメットも洋服のようについついお下がり使ってしまいがちですが、ヘルメットには耐用年数があります。使用から3年を超えたものはメーカーが交換を推奨しています。安易にお下がりを使うのは避けるべきでしょう。新しい物を用意してあげてください。
まとめ
ヘルメットは万が一の際大切な頭部を守ってくれる重要な保護具です。値段やデザインなどだけで選ばず、本来の目的にあっているか、また安全規格をクリアしているか、さらにフィットしたサイズであるかなどに注意して選ぶようにしましょう。
また正しくかぶり、アゴひもなどストラップもキチンと固定するようにしてください。せっかくのヘルメットもしっかり頭部に固定されていなければ本来の機能を果たすことができません。着用方法は必ず守りましょう。
そして、一度でも落下など強い衝撃を与えた場合は、外見上ダメージがなくてもその後の使用は控えてください。ヘルメットは内側の衝撃吸収用ライナーが潰れたり破壊されることで頭部へのダメージを軽減しています。ヘルメットを落下させてしまうと、このライナーが潰れて衝撃吸収機能が失われてしまいます。そのまま使用するのは危険なので必ず交換するようにしてください。
また正しくかぶり、アゴひもなどストラップもキチンと固定するようにしてください。せっかくのヘルメットもしっかり頭部に固定されていなければ本来の機能を果たすことができません。着用方法は必ず守りましょう。
そして、一度でも落下など強い衝撃を与えた場合は、外見上ダメージがなくてもその後の使用は控えてください。ヘルメットは内側の衝撃吸収用ライナーが潰れたり破壊されることで頭部へのダメージを軽減しています。ヘルメットを落下させてしまうと、このライナーが潰れて衝撃吸収機能が失われてしまいます。そのまま使用するのは危険なので必ず交換するようにしてください。
Copyright © ROYAL HOMECENTER Co.,Ltd. All Rights Reserved.



